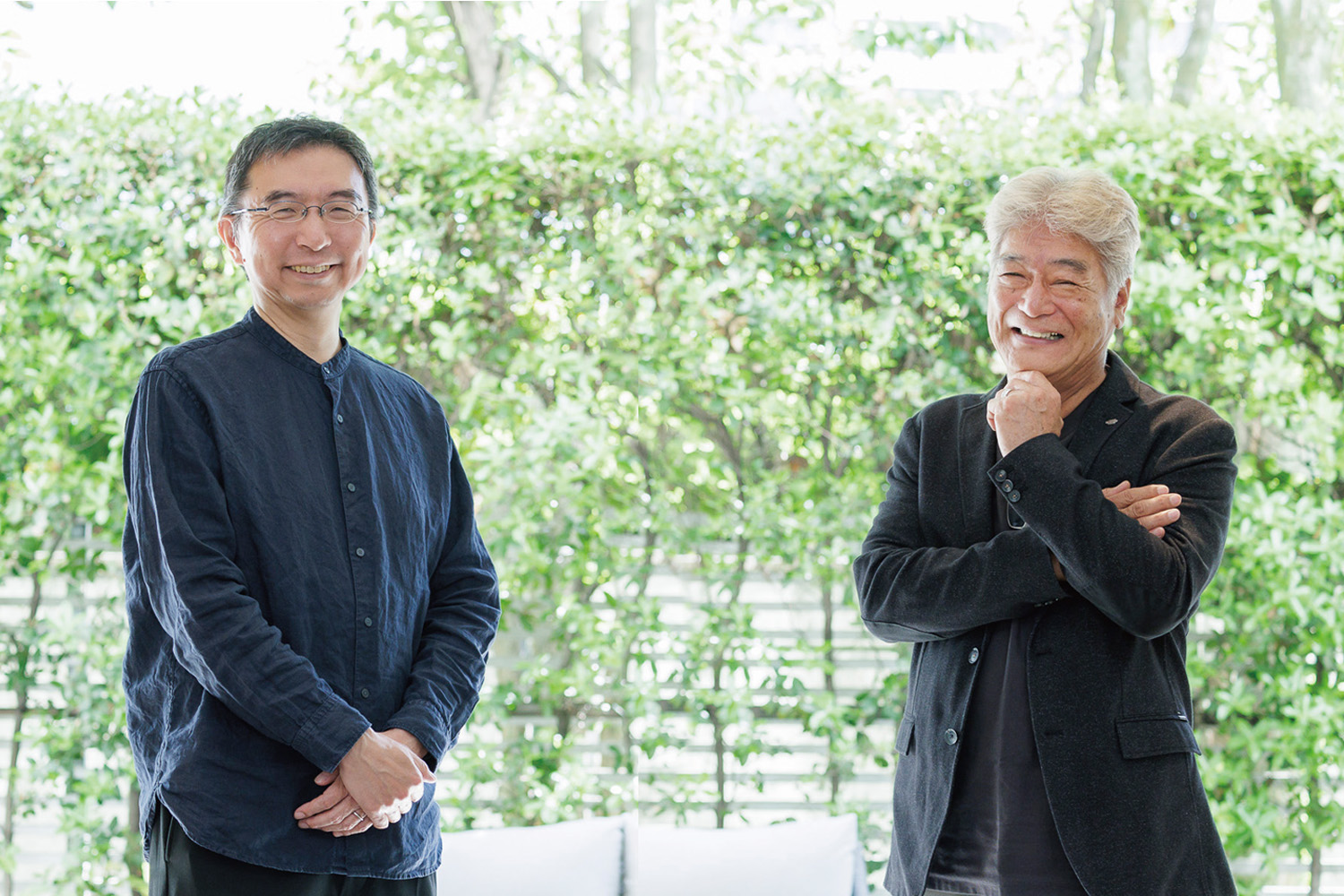
TALK SESSION
藤本 壮介 × 西岡利明
建築とデザイン 未来への視座
社会のあり方や人々の価値観も変化していく中、建築空間は、そして水まわりを含む“住”のデザインは、これからどのような方向に向かっていくのでしょうか。
建築家の藤本壮介氏とSANEI株式会社の代表取締役社長 西岡利明が対談しました。
原点は北海道の自然と父親の書斎にあったガウディの本
西岡:藤本さんは北海道の釧路に生まれたそうですね。北海道は、どこまでも続く空と大地と、冬がとても寒く、まざまざと自然の影響を受ける土地であると思うのですが、そのあたりの幼少期の経験というのは建築の創作に影響しているものなのでしょうか。
藤本:子供だった当時は何も感じていませんでしたが、今思うと影響していると思います。小学2年生になって東神楽に引っ越したのですが、そこで自然に囲まれていろいろ遊び回ったり大雪山が見せる四季折々の表情に感動したりして培ったものが現在の創作活動に無意識ではあるけれども影響しているかもしれませんね。
西岡:やはりそういうものですか。北海道の大自然に囲まれて育ったことが現在の藤本さんのベースを形づくっているのかもしれませんね。それから聞くところによると、何でも中学生の時にアントニオ・ガウディの本を読んで感銘を受けたとか。
藤本:ええ。私の父は医者だったんですけど、医学生時代に絵を描いたり彫刻をしたりしていたらしくて、アートの書物が家にたくさんあったんですね。その中に一冊だけ建築の本があって、それがガウディだったんです。中学2年生ぐらいの時にこれを見て「こんな世界があるのか」と。強烈じゃないですか、ガウディなので。ただ、中高生の当時、興味があったのは建築より物理学だったんです。アインシュタインのように、形のある物ではなく新しい概念を創り出すことに憧れを持っていました。だから大学では物理学を学ぼうと理系に進んだのですが、最初の授業でまったく内容についていけなくて。それはもう挫折とすら言えないぐらいに。すぐにその道は諦めました。そこからかつてのガウディの記憶も蘇って選択したのが建築だったんです。建築の世界を本格的に知ったのはそこからなのですが、どんどんそのクリエイティブな世界にのめり込んでいきました。
西岡:そうだったんですね。建築というのは、ガウディのように自分の作品が100年後、200年後どうなっているのかを考えながら創作するわけじゃないですか。我々も目指すところは、時代を超えて受け入れられるようなものづくりをしたいですし、その点で建築は素晴らしいお手本になります。
藤本:確かに建築には物理的にものが残るという側面もありますし、アインシュタインの理論のように概念として残っていく側面もあります。人の住み方とか、人が集まる場所をどうつくるかといった考え方の部分ですね。それもまた建築ですし、長い時間に耐えうるものでありたいと思っています。
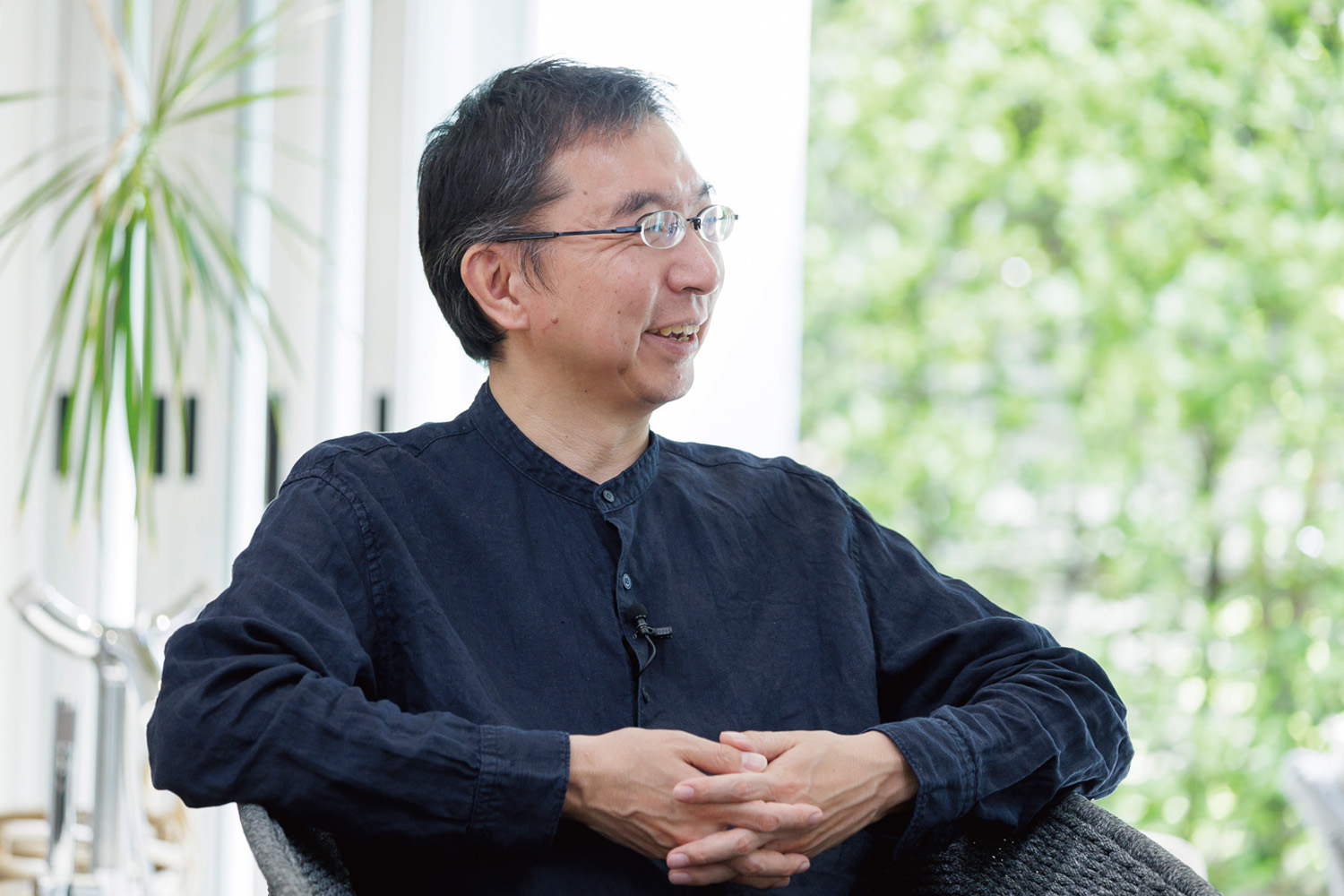
大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」に込めた想い
西岡:ところで2025年はいよいよ大阪・関西万博が開催されますね。我々SANEIもブロンズパートナーとして協賛しているのですが、藤本さんは万博のシンボルとなる「大屋根リング」を手掛けられました。あの巨大な屋根は一体どういった経緯で考えられたものなのでしょうか。
藤本:55年前の大阪万博と違って、今は万博のような特別な場所でなくても最先端のものはどんどん出てきます。では今度の万博の意義とは何か。そのことをじっくり考えてみると、世界情勢が安定しない現代において、それぞれの国が文化・風習を持ち寄ってひとつの場所に集まり、時間と空間を共有するそのこと自体に大きな価値があるのではないかと思えてきました。会場は、そのことを実感できる場所である必要があります。
夢洲に立った時、すごく空が大きくて、ここに来る人はみんなこの空を見上げるんじゃないかと思ったんです。しかもどの国で見る空もつながっているわけですよね。そこから空を円で切り取るアイデアが浮かんできました。
西岡:あの大きな環の中に世界中の人が集まってその瞬間にしかない同じ空を見上げる。建築というより何か詩のようでもあります。
藤本:建築だけだと、地球規模のイベントである万博のテーマを受け止めきれないんです。あの場所は、空が一番のシンボルというわけです。
西岡:私は今でも「太陽の塔」を見ると、小さい頃に月の石を見に行った万博の思い出が蘇ります。同じように、あの大屋根が50年先100年先も継承されていくことを願っています。

人のもつ「曖昧さ」を受け止める
藤本:人間とか人間社会が本来持っている「いい意味での曖昧さ」というのでしょうか。これからの建築は、それを受け止める場としてつくられるようになっていくのではないかと思っています。
西岡:つまり、人に寄り添う建築ということですね。
藤本:ええ。建築が人に何かを強要するのではなくて、建築が人のいろんなことを受け入れてくれるようなイメージです。20世紀は機能主義の時代でしたよね。でも人の活動というのはそれほど機能ばかりではない。効率追求の機能主義が、人の余白を削り取ってしまったのではないかと。
西岡:確かにその通りですね。それがコロナ禍を経た今、私たちの価値観にも変化が訪れている気がしています。
藤本:そうですね。オフィスではなく家で働くことになった時、家があまりにも住むことに機能的に作られているから「どうやって働けばいいんだ?」となりましたよね。人間の活動というのは厳密に区切れるものではなく、もっと柔軟で、横断的です。世の中がそのことを意識するようになったんだと思います。
西岡:今のお話は、私たちのモノづくりにおいても通じる部分があると感じています。機能だけではなく、人間的な部分があってこそ、人はそこに豊かさを感じるのだと思っています。当社では「五感に訴えかけるモノづくり」という考え方を大切にしています。例えばお風呂の水栓であれば水の「音」までもデザインの対象になります。

藤本:それは一体どういう水栓なんですか。何だかとても興味があります。
西岡:京都のお寺などにある水琴窟の音って癒やされますよね。それと同じように水栓から出た水がお湯の水面を打つ音に注目して、研究を続けています。水の出し方。それによって脳内のアルファ波にどう影響するのか。それがリラクゼーションにどうつながるのか―。
藤本:それは面白いアプローチですね。アイデアが刺激されます。
西岡:水栓というのは、建築空間の中で水を空気中に解放する役割を担っています。そして、そのあと水がどう動くかをデザインすることも私たちの仕事と考えています。
藤本:興味深い考え方です。建築家、メーカーという領域の違いはありますが、これからは両者の役割を切り離して考えるのではなく、ライフスタイルやこれからの社会をどのようにデザインしていくのかという大元の部分を、同じ仲間として一緒に議論しながら考えていく必要を感じます。それが最終的にはリアルなプロダクトや建築空間のコンセプトに落ちていく。今回のお話を通して、SANEIさんとはそんなコラボレーションをご一緒してみたいと感じました。
西岡:ええ。ぜひその機会が実現することを私たちも楽しみにしています。
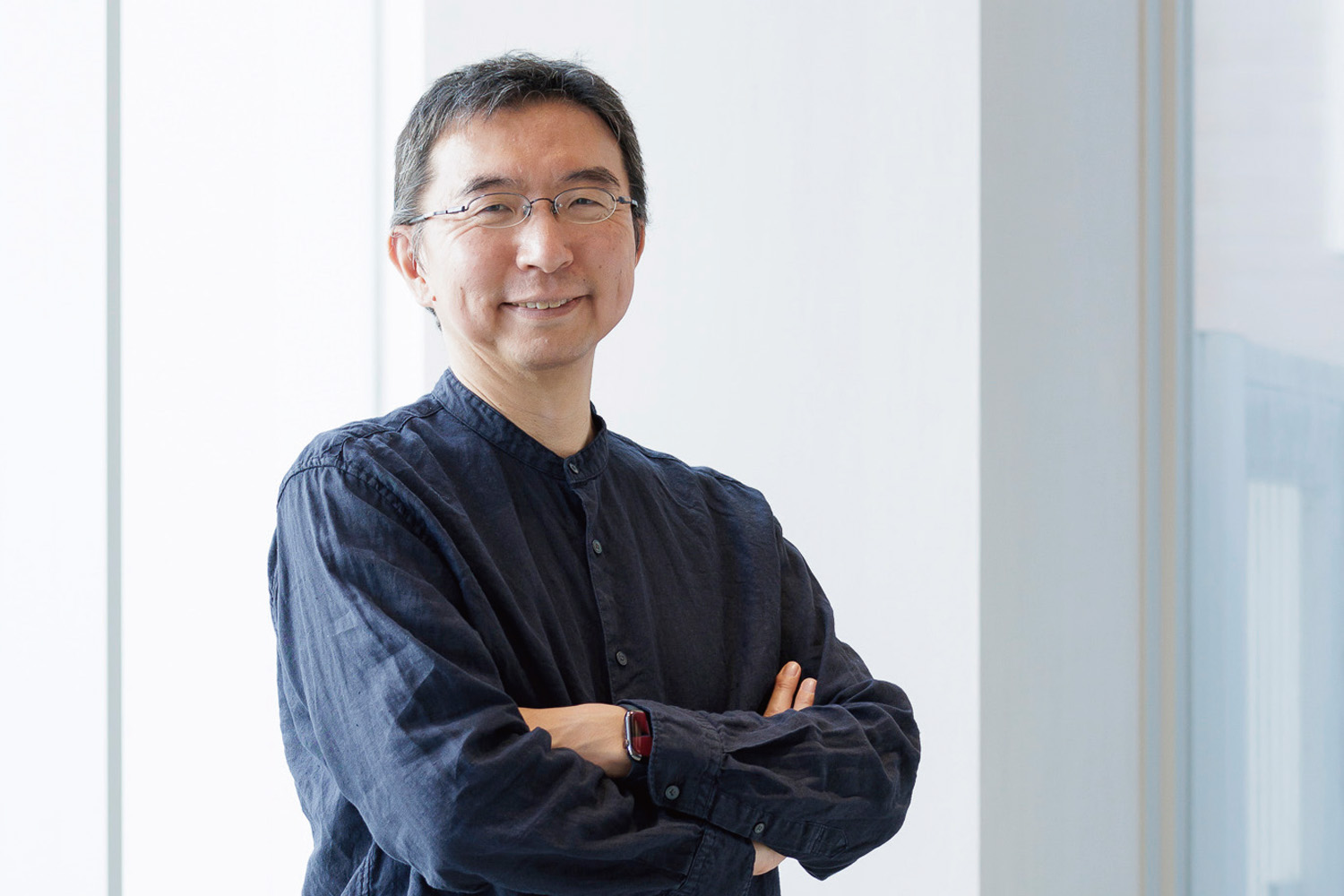
藤本 壮介
1971年北海道生まれ。
東京大学工学部建築学科卒業後、2000年藤本壮介建築設計事務所を設立。2014年フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞(ラルブル・ブラン)に続き、2015、2017、2018年にもヨーロッパ各国の国際設計競技にて最優秀賞を受賞。国内では、2025年日本国際博覧会の会場デザインプロデューサーに就任。2021年には飛騨市のCo-Innovation University(仮称)キャンパスの設計者に選定される。
主な作品に、ブダペストのHouse of Music(2021年)、マルホンまきあーとテラス石巻市複合文化施設(2021年)、白井屋ホテル(2020年)、L’Arbre Blanc(2019年)、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013(2013年)、House NA (2011年)、武蔵野美術大学 美術館・図書館(2010年)、House N(2008年) 等がある。
【関連URL】
・「藤本壮介の建築:原初・未来・森」協賛のお知らせ
https://www.sanei.ltd/news/20250623_10078773/



